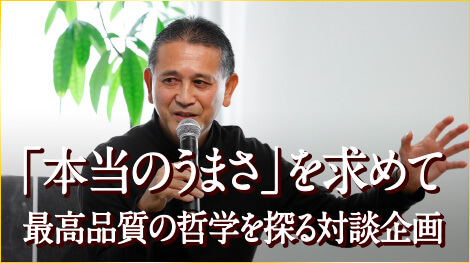田山)今日はお話しできるのをとても楽しみにしていました。ぜひバーミキュラのフライパンを事前に使ってみたいと思っていましたが、タイミング的に買ったら、手元に届くのが3~4カ月ということで、間に合わないな、と思い、貸して頂けないかご相談させて頂きました。フライパンを使ってみた感想ですが、正直おどろきましたね。前評判は高かったので、相当なものだろうと思っていたのですが、まずはシンプルな目玉焼きから作ってみたら、これが今まで作った目玉焼きのなかで最高においしいな、というのがレシピ本通りに作ったらできてしまったんですね。面白いな、と思って、色々理屈も調べてみて、なるほどな、と思いました。最近ですと、私も在宅勤務が多いので、昨日も使う機会があって、ステーキを焼いてみたんですね。本当に今までだったら、例えば肉だったら、何の肉料理にしようか、ハッシュドビーフにしようかな、ビーフストロガノフにしようかな、とか色々凝ったことを考えるんですけど、このフライパンならシンプルにステーキでいいじゃんって言う風に変わったんですね。あまり、ステーキそのものを家で食べる習慣がなかったんですが、やっぱり肉のうま味もしっかり感じられますし、本当に上手に焼けるので、なるほどな、と思って、借り物ではなく、自分のものにしたいな、と思って使っていました。
土方)私も実は、最近はクラフトビール以外飲んでいなかったんですね。そんな状況で、なんの先入観もなく「本麒麟」をいただいたのですが、本当にびっくりしまして、こんなにおいしいんだと思いました。私、ビール類とか新ジャンルとかに限らず、基本的にバーミキュラの料理に合うようなお酒しか飲まないんですよ。クラフトビールの苦みや甘みが好きで、それが合うと思って飲んでいたんですけど、実際本当にびっくりして。最初のコクのある凄く心地のいい苦みと、バーミキュラがいつも凄く大事にしていて、口から食べ物がなくなったあとも続くような甘みとか余韻とか、雑味のなさがですね、それが僕たちがおいしいと思っていることなんですけども、まさに「本麒麟」って、心地よい甘みがずっと続きながら、雑味がないんですよ。バーミキュラの味のコンセプトに凄く合っていて、例えば、バーミキュラの料理って、結構きつい調味料はあまり合わないんですよ。凄く優しい、いつまでも続く甘みが特長なので。(本麒麟を飲んでみて)ジャンルってどうでもいいな、って凄く痛感させられました。それぐらいおいしかったです。
田山)端的に言うと、どこが違うかっていうか、どう表現されますか?
土方)そうですね。五感それぞれであるんですが、味覚本来の話でいくと、やはり余韻ですね。最初にもインパクトがあるんですが、口からなくなった後も、ずーっと甘みが、心地よい甘みが残っていて、雑味を感じない。やっぱり、化学調味料の料理の味って、一気に感じるおいしさはあるけど、後味は、噛んだガムのような味になってしまう。そこを凄く気を付けています。
田山)フライパンが違うだけでこんなに味が違うのか、って正直凄く驚きましたね。後味、うま味が残るって言うのは、どう言う理屈なんですかね?
土方)我々も開発当時から、とにかく素材本来の味を引き出すものをつくるんだ、とやってきまして、ただのそれって言葉だったりとか、体験で感じた、こういうものがバーミキュラらしい味というのがありまして、実はそれ、うちの社員みんなが感じていることなんですよ。専属シェフが料理を作ったりすると、「これはバーミキュラらしくない」とか「これはバーミキュラらしい」とか言うんですけど。結局はやっぱり、雑味のなさとか、味に関しては、それが皆の共通項だと思います。
田山)余計なものがないっていうところが、むしろ本来素材が持っている味を引き立てる。凄く分かります。我々も凄くそれを意識していて、いきなり本題に入ってしまうんですけど、おいしいものは、その場だけでおいしいではだめだと思うんですね。日常の普段使いも、また飲みたくなる、と思っていただく事、実はアフターテイストがとても大事だと思っています。飲んだときのおいしさも大事ですが、実はそこの違いがめちゃめちゃ大きい。ですので、今の話をお聞きして、共通するものがあると思って聞いていました。