 ビールの歴史
ビールの歴史
メソポタミアでの
ビールのつくりかた
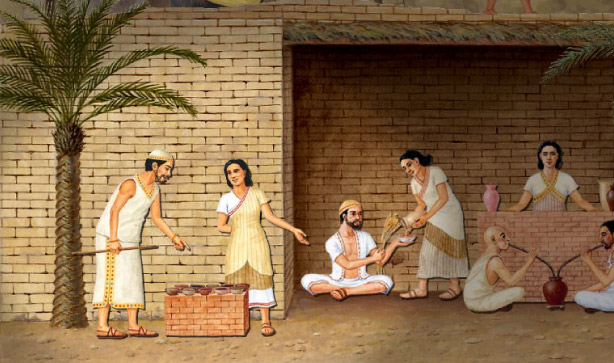
ここで改めて古代メソポタミアにおける基本的なビールのつくり方を確認しておきたい。
まず、大麦を発芽させた麦芽を乾燥、そこに古代種の小麦であるエンマーコムギの粉を混ぜて、バッピルという固いパンを焼き上げる。このバッピルを砕いて湯で溶き自然発酵させたのが、当時の一般的なビールであり、人々はこれを「シカル」と呼んだ。
ひとくちにビールと言っても、その種類は当時からさまざまであった。バッピルの焦がし方や麦の配合を変えたり、各種スパイスや季節ごとの果実を加えることで、ビールの味はもちろん、その呼び名までもが変化したのである。
「とりあえずシカル」
と客が注文すれば、居酒屋の女将は「はいよ」と一般的なビールを差し出すのであり、
「今日は疲れたからビーカルにするわ」
とくれば、「ほどほどにね」と言いながら強いビールを出すのである。時には、訳あり風の「いちげんさん」が現れ、こうたずねることもあるだろう。
「カッシはあるかい」
すると女将は「この男、通だわ」と思いながら、取って置きの黒ビールを出すのであり、
「今どきカッシグ置いてないなんて、ありえなくね?」
と当世風の若者が半笑いで言えば、「うるせえ、ガキ」と内心毒づきながらも、三軒隣の店で評判の赤ビール「カッシグ」を飲んでみようかと考えるのである。無論、すべての発言は想像にもとづくものである。
そんななか、「カッサガサーン」と呼ばれるビールは、王侯貴族のみが飲むことを許された、最上級のビールとされていた。
「ああ、死ぬまでに一度でいいから、カッサガサーンを飲んでみたいものだ」
そんな嘆きが、酔っぱらった客たちの間で、夜な夜な交わされたであろうことは想像に難くない。そして、いい加減つきあうのに面倒くさくなった女将は、決まってこう答えるのである。
「わかったから、早く帰っておくれ!」

