 ビールの歴史
ビールの歴史
グルート権とグルートビール
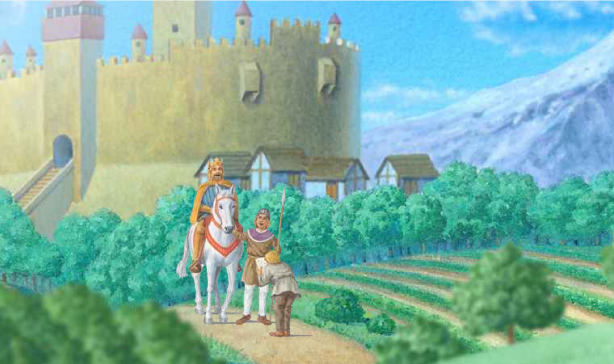
ホップがビールの主原料として使われるようになる以前、中世ヨーロッパではヤチヤナギやペパーミント、月桂樹など、様々な薬草(ハーブ)をビールに混入していた。それらはビールに独特の苦味や風味を与えるだけでなく、醸造過程で雑菌の繁殖を抑え、保存性を高めるのに大切な役割をはたしていたのである。
こうしたビールに配合するハーブ類を「グルート」と呼んでいた。封建社会の領主たちは、領外の湿地帯に自生するハーブの特権を押さえ、グルートの生産と販売の権利、すなわち「グルート権」を独占し、人々に専売することで多くの利益を得ていた。この時代、修道院もまた財源確保を目的としたビールの醸造販売をおこない、両者は商売敵となって激しい利権争いを演じるようになった。
領主「どういうことだ、こないだの凶作で穀物が不足しているというのに、修道院ビールはどんどん出回っているではないか」
醸造主「へい、やはりあちらには神様のご加護があるようで。人手から原料から、なんでも安く手に入るんでさあ。おまけにビールの味も上等だし、これは敵いませんわな」
10世紀末の文書資料には、神聖ローマ帝国(現ドイツ)の皇帝オットー3世が、ユトレヒト司教座教会に対してグルート権の譲渡を認めた権利書が残っている。このように各種特権を行使した修道院ビールは、封建社会において世俗的な成功を収め、最盛期には1.000以上の修道院ビールが競合するような状態となった。
しかしこうした利権争いも、のちにホップが新たな原料として普及するようになると急速に沈静化。また来たる市民社会の勃興と、のちの宗教改革へと続く教会不信により、修道院もまたその影響力を、次第に低下させていく運命にあるのであった。

